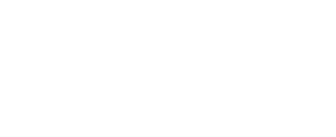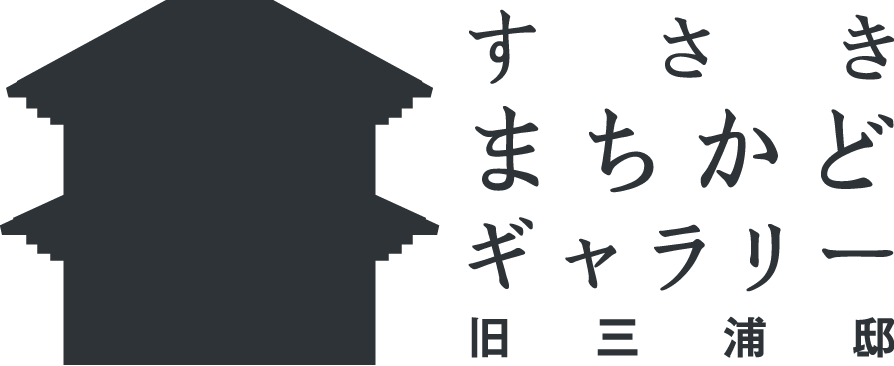昨日まで昼間はぽかぽかしていましたが、今日は冬らしい風が吹いていますね。
さて先日のまちかどギャラリーの近くの商店街で行われた
サカナ文化祭のレポートを書いていこうと思います。
2025年11月15日(土)と16日(日)にはサカナ文化祭が開催されました。
キッチンカーやマルシェ、大道芸のステージやこども広場などが行われていました。
ちょうど大道芸のパフォーマンスが行われているところです。

高知信用金庫さん前のこども広場では、おサカナ飛ばしを楽しんでいる様子も。

商店街はにぎわいをみせておりました。
すさきまちかどギャラリーの展示では、
「竜踊りと土佐にわかに見るー須崎市西町の祭りと文化ー」
「竜踊り」と「土佐にわか」の展示が11月30日まで行われています。
「土佐にわか」とは…
無声の人形劇です。昔話や怪談、歴史上の出来事などの一場面を人形で表現する高知独特の文化であり、
明治から大正時代初期にかけて県内各地の夏祭りなどで盛んに公開されていたそうです。
昭和に入ると姿を消していましたが、昭和28年に須崎の西町の有志により結成された「西栄会」が
大師祭の復活にあわせて「土佐にわか」を余興として再び蘇らせることを決めたのです。
夏祭りにふさわしく、涼を呼ぶ意味をこめて、昔から怪談話が多かったそうです。
しかし、新型コロナウィルスの流行以降は製作が一時中断しています。
かつて高知県内で当たり前のように見られた「土佐にわか」は、今も須崎の大師祭にその灯を残し、再び動き出すときを待っています。
「大師祭」「竜踊り」とは…
須崎市西町には弘法大師ゆかりの大善寺があり、いつの頃からか、
西町では弘法大師空海の月例忌日の前夜に、宵祭りとして「大師祭」が行われるようになりました。
大正期の大師祭では西町の各家庭から持ち寄った物干しざおを街路の上空に渡し、
赤い丸提灯を吊るした華やかな飾りつけが施されていました。
さらに露天商が立ち並び、町全体が大変な賑わいをみせていたといいます。
しかし、長く続いてきたこの大師祭も、太平洋戦争の影響により一時中断してしまいました。
戦後の混乱が落ち着くと西町の有志が立ち上がり、「西栄会」を結成。
彼らの尽力により昭和28年(1953年)に大師祭は見事に復活を遂げました。
そして、復活から4回目となる昭和31年(1956年)西栄会では祭の中心となる出し物について
検討を重ねていました。その年の5月14日、高知市で開催された「日本専門店会全国大会」の
街頭パレードで披露された長崎県の「蛇踊(じゃおどり)」に深い感銘を受けたのです。
これをきっかけに、西栄会では大師祭の出し物を蛇踊を参考にした「竜踊り」とすることを決定しました。
その年の8月25日(旧暦7月20日)竜踊りは大成功を収めました。
現在、大師祭は毎年8月20日に開催されています。
竜踊りは、世代を超えて受け継がれる須崎の伝統文化として、今も多くの人々の心を魅了し続けています。

須崎市西町の「土佐にわか」をご存知の方は「懐かしい」と
おっしゃってご覧になられている方もおりました。
ギャラリーすぐ入ってホールには「土佐にわか」の「新荘川の河童」が展示されています。
通りがかった方々は商店街の通りから見える展示に足を止められて
「かっぱだ」「目が光ってる」とさまざまに見入られていました。


しんじょう君も新荘川の河童と遭遇。
中でも蔵に展示された「土佐にわか」の「ろくろ首」は
びっくりして泣いてしまう小さいお子さんもおりました。
小学生でも初めて見たときは「怖かった」とのことでした。

ホールから入って和室の方では「土佐にわか」の貴重な写真のアーカイブや
「竜踊り」の展示も和室の奥にございます。

11月16日(日)には雅楽のワークショップもまちかどギャラリー和室で開催されました。

中庭に面した場所で開催されていたため、興味を持たれた方が数多く体験されていました。
ワークショップ中は雅な音が流れておりました。
表門のほうには、あの映画の「土佐にわか」の展示もあります。
11月30日まで展示しております。
ぜひすさきまちかどギャラリーにお越しください。
このブログを書いた人
最近書いた記事
 お知らせ2026年1月16日現代地方譚13開催のお知らせ
お知らせ2026年1月16日現代地方譚13開催のお知らせ ワークショップ2026年1月4日新年のご挨拶
ワークショップ2026年1月4日新年のご挨拶 お知らせ2025年12月24日年末年始のお知らせ
お知らせ2025年12月24日年末年始のお知らせ ワークショップ2025年12月17日クリスマスワークショップ
ワークショップ2025年12月17日クリスマスワークショップ