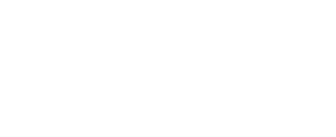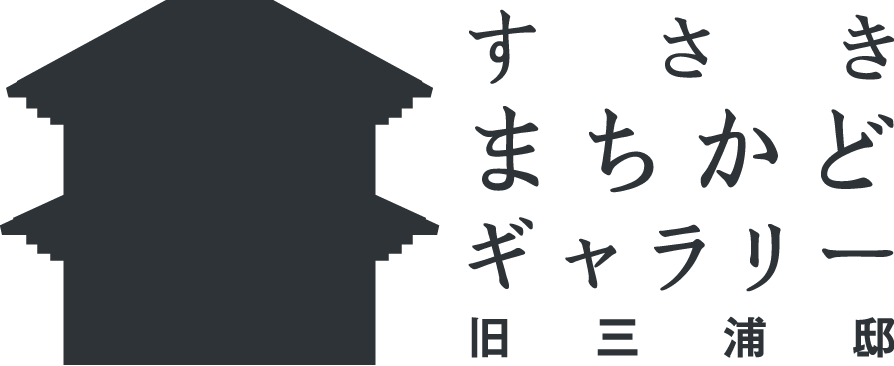三浦邸を知ろう!キーワードラリー
蔵/金庫
内部にふたつの大きな鉄製金庫を構える蔵は二階建てになっており、開口部以外は土佐漆仕上げになっています。格子状の床が用いられ、床下は通気のために深くスペースがとられています。向かって右側の金庫は、60年間ほど鍵が施錠されたままの状態で「開かずの金庫」になっていましたが、テレビ番組の企画により鍵師さんに開錠していただきました。金庫の中には、明治期から昭和初期ごろまでの三浦家がおこなっていた事業に関する書類などが収められていました。
あか②
象の欄間
花や鳥、風景が彫り込まれたものが多い欄間ですが、三浦邸では象が彫り込まれています。明治時代後期につくられたものと考えられており、象を見る機会の少なかった時代のものとして、とても珍しく貴重な欄間といえます。
あか③
壁についた扉
この扉はなんのためにあるのでしょうか?扉を開けると戸袋に通じており、雨戸の出し入れがしやすくなっています。
あか④
表門・塀
道路から主屋玄関へと通じる門は ケヤキの良質な木材が多用されています。亀甲石積(六角形に切った石を積み上げていく積み方)の塀の基礎などが景観を意識した丁寧なつくりとなっています。
(画像の下にテキスト)塀の化粧桟には意匠性を⾼める”名栗”という表⾯ 独特の削り痕を残す加工技術が施されています
平成28(2016)年、三浦邸住宅は「店舗」「主屋」「蔵」「離れ」「表門・塀」「ブロック塀」の6構造物が国の登録有形文化財に指定されています。
国の登録有形文化財登録有形文化財とは、建築物・土木構造物などで、建設後50年を経過し、歴史的景観に寄与しているものや、造形の規範となっているもの、再現することが容易でないものなどの条件を満たすものが認定されます。
あか⑤
しんじょう君のマンホール
すさきまちかどギャラリーでは、「しんじょう君」のマンホールカードを配布しています。
しんじょう君は須崎市の新荘川で最後に目撃されたニホンカワウソがモチーフの須崎市のマスコットキャラクター。須崎のB級グルメ「鍋焼きラーメン」の帽子を頭にかぶっています。
下水道広報プラットホーム(GKP)が企画・監修するマンホールカードは、マンホールのふたのデザインを紹介するもので、全国の自治体で発行されています。須崎市観光協会では、市の花「ヤマザクラ」と鳥「カワセミ」がデザインされたマンホールカードが配布されています。
あか⑥
ブロック塀
モルタルブロックと和風の瓦屋根が融合され、屋敷としての景観を損なうことのない近代らしい形式の塀です。三浦邸住宅は「店舗」「主屋」「蔵」「離れ」「表門・塀」「ブロック塀」の6構造物が国の登録有形文化財に指定されています。
国の登録有形文化財登録有形文化財とは、建築物・土木構造物などで、建設後50年を経過し、歴史的景観に寄与しているものや、造形の規範となっているもの、再現することが容易でないものなどの条件を満たすものが認定されます。
あか⑦
証券会社時代の黒板
江戸時代末期から続く商家の三浦家では、製紙業、酒造業、米穀業、海運業、林業、金融業など多岐にわたる事業が行われていました。大正中期に建てられた一面黒塗りの建物は店舗として使用され昭和30年代ごろの数年間、証券会社が経営されていました。
あか⑧
てづくりのガラス
むかしは職人さんの手により、ひとつひとつ手作りされていました。手作りならではの不規則な揺らぎがあったり、気泡があったり同じ形はふたつとありません。ガラス越しに庭の木がゆらゆらと揺らいで見える様子はとても味わい深いですね。
あか⑨
造りつけのタンス
取手や円形の飾り部分にはデザインが施され、贅沢なつくりとなっています。また、引き出しごとに鍵穴があり、鍵がかけられるようになっています。
あお①
鍵(ねじ締り錠)
窓枠に金属の棒をさし込み、キュルキュルキュルとまわしてカギをかけます。大正時代に発明された日本独自のカギですが、アルミサッシの登場により次第に姿を消していってしまいました。
あお②
格天井
木をたてよこに組み、その上に板を張った作りの天井。お寺の建物や書院造りなど、格式の高い部屋に使われます。店舗だった建物にはうるし塗りの格天井が用いられ、豪商の名残をとどめています。
あお③
欄間の船
現代地方譚2(2014年)参加したアーティスト。持塚三樹さんの作品の一部です。 2014年の三浦邸の改修工事の際に出た木材で作られました。
現代地方譚とは
さまざなジャンルの表現者が須崎に滞在し、リサーチや作品制作を行う取り組みです。2014年から現代美術を中心にアーティストの招聘と発表を行い、2018年以降は音楽家や演劇人も招いた創作を行っています。「(たん)」とは物語のこと。アーティストの視点を手掛かりに、物語を紡ぐように“いま”の須崎の在りようを皆で語らい、地域の将来を想像するアートプログラムです。毎年1月~2月までの約1カ月間、開催されています。現代地方のドキュメントブックをご希望の方は、スタッフまでお声掛けください。
あお④
右瓦と左瓦のふき分け
高知県は台風や大雨の多く、雨や風が強くふきつけます。昔の工法では瓦と瓦のすき間から雨水が入ってしまい、建物が傷んでしまいます。それを防ぐために、海沿いの地域では風向きに応じて左右のふき分けがされていました。土佐の風土に合わせた伝統的な瓦のふき分け工法は、三浦邸のほか高知県内でも見ることができます。歴史的な建物を見かけたら瓦にも注目してみてくださいね。
あお⑤
Southward
現代地方譚3(2015年)に参加したアーティスト・磯谷博史さんの作品です。 時計の発達は北半球で見るときの太陽の動きによって変わる影「日時計」が基になっています。そのため、時計の回り方は右回りになりました。もし南半球で時計が発明されていたら、この作品のように左回りになっていたかもしれません。私たちの生活の規範の多くが技術や経済が進んだ一部の地域の価値観によって規定されていることを表しています。描かれている時間は作品ができあがった時間だそうです。
現代地方譚とは
ざまざなジャンルの表現者が須崎に滞在し、リサーチや作品制作を行う取り組みです。2014年から現代美術を中心にアーティストの招聘と発表を行い、2018年以降は音楽家や演劇人も招いた創作を行っています。「(たん)」とは物語のこと。アーティストの視点を手掛かりに、物語を紡ぐように“いま”の須崎の在りようを皆で語らい、地域の将来を想像するアートプログラムです。毎年1月~2月までの約1カ月間、開催されています。現代地方のドキュメントブックをご希望の方は、スタッフまでお声掛けください。
あお⑥
三浦家の屋号
「すさきまちかどギャラリー/旧三浦邸」は、江戸時代末期から続く商家・三浦家の住まいと、店舗「三浦商店」を活用した建物です。 多岐にわたる事業をおこなっていた三浦家では、ひし形の中に「上」とかかれたマークは本店が使用していました。ひし形の中に「中」とかかれたマークも存在しています。
三浦家の当主は代々“三浦重作”を襲名していました。 安政3(1856)年生まれの5代目三浦重作は、親戚の三浦安太郎とともに、それまで大阪で仲介料を取られていた土佐和紙の東京直移出を成功させ、その後の土佐和紙の販路を飛躍的に拡大させた紙業界の立役者です。 明治30年代にはコウゾ・ミツマタなどの和紙の原料や製品を商い、朝鮮半島まで船をだすようになり明治40年ごろには高知県屈指の大実業家になりました。海運業、林業、酒造業、米穀業、金融業など多岐にわたる事業がおこなわれ、須崎の町の発展に大きく寄与しました。
あお⑦
郵便受け
外壁に備え付けの郵便受け。投函された手紙は内側から取り出せる仕組みになっています。
※文化財保護のため、お手を触れないようにお願いします。
あお⑧
蔵/金庫
内部にふたつの大きな鉄製金庫を構える蔵は二階建てになっており、開口部以外は土佐漆仕上げになっています。格子状の床が用いられ、床下は通気のために深くスペースがとられています。向かって右側の金庫は、60年間ほど鍵が施錠されたままの状態で「開かずの金庫」になっていましたが、テレビ番組の企画により鍵師さんに開錠していただきました。金庫の中には、明治期から昭和初期ごろまでの三浦家がおこなっていた事業に関する書類などが収められていました。
あお⑨
松の木の縁側
かつて三浦家が所有していた蔵の梁として使われていました。2014年の改修工事の際に、三浦家の番頭さんが大切に保管されていていたものを寄贈していただき、現在は濡れ縁として活用されています。